[経歴]
2012年3月 兵庫医科大学医学部 卒業
2012年4月 高知医療センター勤務
その後、大手美容外科にて院長を歴任
2024年2月 いびきのクリニック入職
2024年11月 いびきのクリニック梅田院院長となる
- いびきのクリニックTOP
- いびきのコラム
- 睡眠外来とは?受診するべき症状やメリット、クリニック選びのポイントを解説
睡眠外来とは?
受診するべき症状やメリット、
クリニック選びのポイントを解説
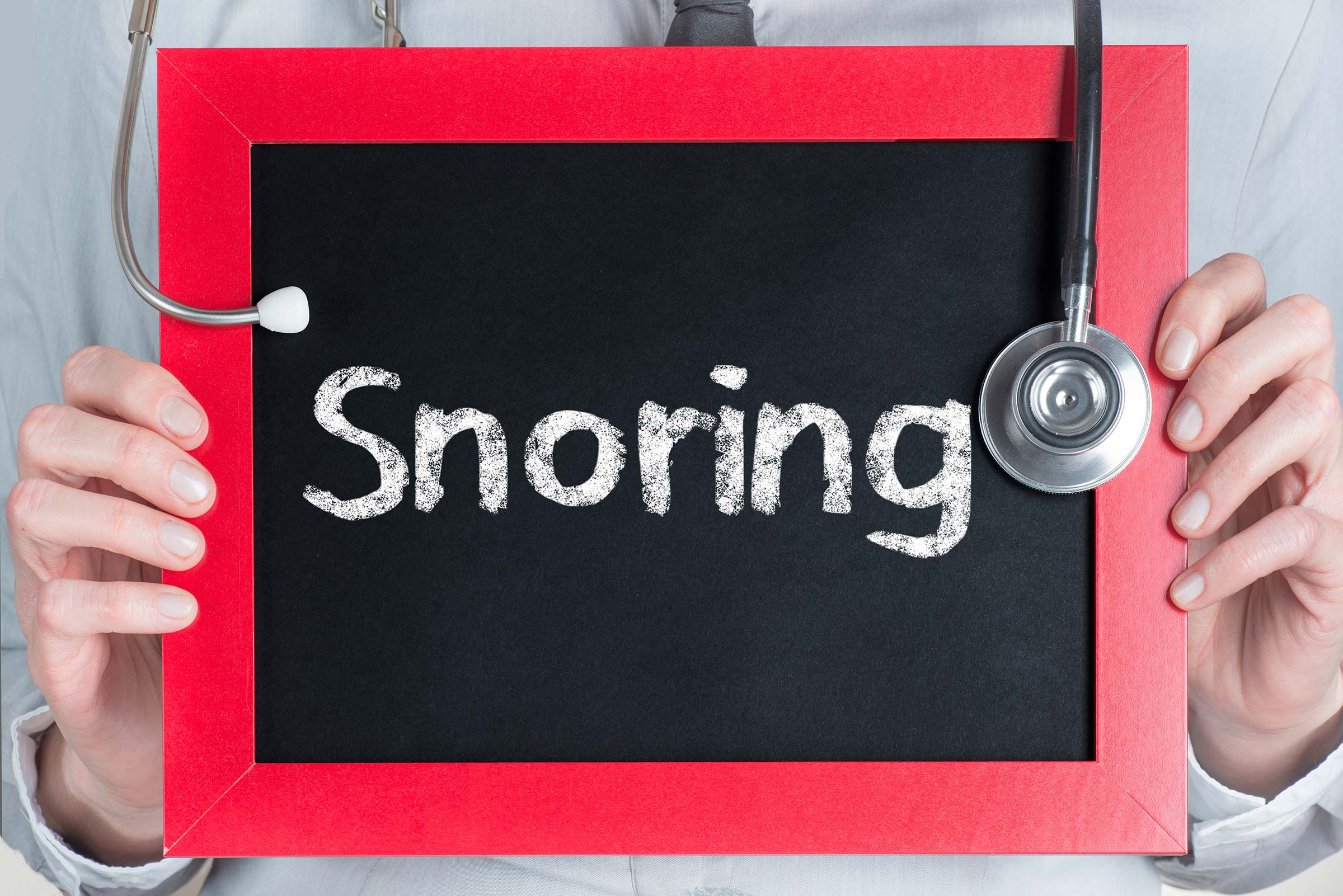
睡眠は健康のために重要で、心身ともに疲労を回復してくれます。しかし、その睡眠を妨げる問題を抱える方も多くいらっしゃいます。
睡眠障害がある方にとって睡眠外来は専門的な診療やサポートを受けることができる重要な施設です。睡眠外来を受診することで、睡眠障害や関連する症状の改善に向けた一歩を踏み出すことができます。
この記事では、睡眠外来を受診すべき症状やクリニック選びについて解説します。
監修医師情報

睡眠外来とは?

睡眠外来とは、不眠症や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害に対応する診療科です。患者さまは、睡眠外来を受診することで、専門家の診断や治療を受けることができます。また、睡眠外来では、睡眠に関する検査や相談も行われます。
睡眠外来で治療することで睡眠障害の改善が期待できます。
睡眠外来はどんな症状の時に行けば良い?
では、どのような症状が現れたら睡眠外来に行くべきなのでしょうか。
- 持続的な不眠症
- 眠りにつくのが難しい、寝つきが悪い、夜中に何度も目が覚めるなど、長期間にわたって睡眠に問題がある - 過度の眠気や昼間の眠気
- 日中に過度の眠気を感じる、仕事や運転中に眠気が襲ってくるなどの症状がある - いびきや無呼吸の症状
- 寝ている間にいびきがひどい、伴に無呼吸の症状がある - 睡眠中の異常な状態
- 睡眠中に異常な状態を感じる、夢を見ても休息感が得られないなどの症状がある
これらの症状やサインがある場合は、睡眠外来を受診することで適切な診断と治療を受けることができます。
睡眠外来に行くメリットとは?

睡眠外来では、睡眠障害や関連疾患の診断や治療を専門とする医師のもと、患者一人ひとりの状況に合わせて適切な診察内容や検査方法が選択されます。
睡眠外来を受診することで、睡眠に関する専門的なアドバイスや治療を受けることができるため、睡眠障害や関連疾患の改善につながる可能性が高まります。
睡眠専門医の存在は、睡眠に関する問題を抱える患者さまにとって重要であり、適切な診断と治療を受けることができるため、健康な睡眠を取り戻す手助けとなります。
睡眠外来を選択することで、症状の改善への近道になることは間違いありません。
睡眠外来で治療できる病気は?

睡眠外来で治療できる病気は何があるのでしょうか? 代表的なものをいくつか紹介します。
不眠症
不眠症は、睡眠に関する問題であり、十分な睡眠を得られない状態を指します。
不眠症の原因はさまざまであり、生活習慣や心理的要因、身体的な疾患などが関与しています。
不眠症を改善するためには、まず生活習慣の見直しが重要です。規則正しい生活リズムを保ち、睡眠環境を整えることが大切です。さらに、専門家の指導のもとで行われる認知行動療法や睡眠薬の適切な使用も不眠症の治療法として考えられます。
不眠症は放置すると日常生活に支障をきたすだけでなく、健康リスクを高める可能性もあるため、早めの対策が重要です。
入眠障害
入眠障害は、寝つきが悪く、なかなか眠りにつけない状態を指します。布団に入ってから30分~1時間以上経っても寝付けない状態だと、入眠障害かもしれません。
入眠障害は、ストレスや不安、環境の変化などが原因で起こることが多いです。寝る前のリラックスや睡眠環境の整備が重要です。
中途覚醒
中途覚醒は、夜中に何度も目が覚める症状です。中途覚醒の特徴としては、夜中に何度も目が覚める、眠りが浅い、朝早く目が覚めてしまうなどがあります。
ストレスや睡眠環境の悪化、身体的な不調などが中途覚醒の原因となることがあります。
中途覚醒は、睡眠の質が低下し、日中の疲労感や集中力の低下につながります。規則正しい生活リズムや睡眠環境の整備が改善のポイントです。
過眠症
過眠症は、過剰な睡眠欲求や日中の過度な眠気を特徴とする状態です。過眠症の特徴としては、日中に眠気を感じる、昼間に居眠りをしてしまう、夜間の睡眠時間が長くても疲れが取れないなどが挙げられます。
遺伝的要因や睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害、身体の疾患、うつ病などが過眠症の原因として関連していることがあります。また、最近では新型コロナウイルス感染症の後遺症としても過眠の可能性がでてきました。原因不明の場合は特発性過眠症といわれます。特発性過眠症は遺伝的背景があることがわかっています。
過眠症は、その治療法が確立されておらず、難病とされています。そのため、適切な睡眠時間を確保し、規則正しい生活リズムを整えることが重要です。
ナルコレプシー
ナルコレプシーとは、突然の睡魔や昼間の過度な眠気、筋肉の弱まりなどを特徴とする睡眠障害です。
脳の覚醒と睡眠の調節に関わる神経伝達物質の異常がナルコレプシーの原因とされています。
ナルコレプシーの根治治療は確立されておらず、生活習慣の改善や薬物療法が用いられます。
ナルコレプシーは、本人や周りが病気とわからないことが多く、だらしないや、やる気がないなどと誤解されることがあります。日中によく寝てしまうなど心当たりがある場合は、一度クリニックを受診してみてはいかがでしょうか。
レム睡眠行動障害
レム睡眠行動障害は、睡眠中に起こる異常行動や夢遊病の一種です。通常、レム睡眠中は筋肉が麻痺しているため、夢の内容に合わせて動くことはありませんが、レム睡眠行動障害の人は夢の内容に合わせて暴れたり、叫んだりすることがあります。これにより、自傷や他者への危害を加える可能性があるため、周囲の安全を確保するための対策が必要です。
レム睡眠行動障害は主に中高年の男性に多く見られますが、女性や若年層にも発症することがあります。原因としては、脳の神経伝達物質のバランスの乱れや神経変性疾患との関連が指摘されています。
概日リズム睡眠障害
概日リズム睡眠障害は、体内時計と外部の日常リズムとの調和が取れなくなることで生じる睡眠障害です。例えば、時差ぼけや夜勤勤務などが原因で生活リズムが乱れ、睡眠時間や質に影響を及ぼすことがあります。
この障害は、睡眠相前進障害(ASP)、睡眠相後退障害(DSP)、非24時間型睡眠覚醒障害(Non-24)などのタイプに分類されます。
治療法としては、光療法や睡眠薬の使用、生活習慣の改善などが行われます。正確な診断と適切な治療が重要です。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群の主な症状には、夜間のいびきや一時的な無呼吸、朝起きた時の頭痛や倦怠感、日中の眠気などが挙げられます。これは、睡眠中に気道が一時的に閉塞し、正常な呼吸が妨げられることが原因です。肥満や気道の狭窄、睡眠姿勢などがリスク要因として関連しています。
睡眠時無呼吸症候群は重篤な疾患であるため、早期の診断と適切な治療が重要です。症状がある場合は、睡眠専門医のもとで適切な検査や治療を受けることが推奨されます。
睡眠外来ではどんな治療をする?

睡眠障害は、睡眠の質や量に問題が生じる状態を指します。慢性的な睡眠障害は健康に悪影響を及ぼす可能性があります。睡眠外来では、様々な治療法が提供されています。
【ナステント治療】
ナステント治療は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)や睡眠時無呼吸症(SDB)の治療法の一つです。この治療法では、患者さまが寝ている間に鼻腔内に特殊なステント(チューブ)を挿入し、気道の開放を促します。
ナステント治療の主な仕組みは、気道の拡張と支持です。ナステントを挿入することで、気道が狭まるのを防ぎ、空気の流れをスムーズにします。これにより、睡眠中に起こる無呼吸や低呼吸の頻度や重症度を軽減する効果が期待されます。
ナステント治療は、他の治療法と比較しても効果が高いとされています。ただし、個人によって効果が異なる場合もありますので、専門医との相談を重視することが重要です。
【マウスピース治療】
マウスピース治療は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)や軽度から中等度の睡眠時無呼吸症候群(OSA)の患者に効果的な治療法として知られています。
具体的な適応症例としては、以下のような症状や状況が挙げられます。
- 軽度から中等度の睡眠時無呼吸症候群(OSA)の患者
- いびきや睡眠中の呼吸困難を訴える患者
- CPAP治療が適応できない患者
- 歯科医師の指導のもとで適切な装着が可能な患者
マウスピース治療は比較的簡便な治療法であり、装着感も比較的良好なため、患者の満足度が高いとされています。
【CPAP治療】
CPAP治療は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)や睡眠時無呼吸症候群併発症(SASB)などの疾患に対する主要な治療法の一つです。
CPAP治療のメカニズムは、患者が睡眠中に鼻や口から装着したマスクを通じて、一定の陽圧の空気を気道に送り込むことで、気道の閉塞を防ぎ、正常な呼吸を維持することにあります。この陽圧の空気が気道を開いて、気道の振動や閉塞を防ぎ、睡眠中の呼吸を安定させます。
CPAP治療の効果は、睡眠中の無呼吸や低呼吸を改善し、酸素飽和度を安定させることで、睡眠の質を向上させることが期待されます。これにより、日中の眠気や倦怠感の軽減、集中力や記憶力の向上、心臓や血管系への負担軽減などの効果が得られるとされています。
【レーザー治療】
レーザー治療は、口蓋垂や扁桃の一部をレーザーで切除することで、気道の通りを改善し、睡眠時無呼吸症候群(SAS)やいびきの改善を図る治療法です。
レーザー治療の有用性は、手術の際の出血や痛みが比較的少ないことが挙げられます。また、手術時間が短く、入院が必要ないため、比較的簡便な治療法と言えます。さらに、レーザー治療は従来の外科手術よりもリスクが低いとされています。
一方で、レーザー治療にはリスクも存在します。手術後に腫れや痛み、出血、感染症などの合併症が起こる可能性があります。また、効果が一時的で持続しない場合もあるため、定期的なフォローアップが必要となります。
レーザー治療は、特定の症例において有用な治療法であると言えますが、リスクを理解した上で適切な判断をすることが重要です。睡眠外来での専門医の指導のもと、適切な治療法を選択することが大切です。
【外科的手術による治療】
外科的手術は、通常は他の治療法が効果的でなかったり、重症の場合に検討されます。
外科的手術の適応としては、主に以下のような症例が挙げられます。
- 睡眠時無呼吸症候群(SAS)の重症例
- 上気道閉塞が原因となる睡眠時無呼吸症候群
- 特定の解剖学的異常が原因となる睡眠障害
外科的手術による治療は、一般的には他の治療法よりもリスクが高く、合併症の可能性も考慮される必要があります。成功率は症例や手術方法によって異なりますが、適切な患者に対して行われた場合、効果が期待されることもあります。
【薬物療法】
薬物療法は、睡眠障害の症状を軽減するために使用される方法の一つです。睡眠導入剤や抗不安薬などが一般的に処方されますが、長期間の使用による依存症や副作用に注意が必要です。医師の指導のもとで適切な薬物療法が行われることが重要です。
【認知行動療法】
認知行動療法は、睡眠障害の改善に効果的な治療法の一つです。睡眠に関する誤った信念や行動パターンを改善し、健康的な睡眠環境を整えることを目指します。睡眠日誌の記録やリラクセーション法の習得など、患者自身が積極的に取り組むことが重要です。
短期的な効果だけでなく、長期的にも睡眠の質を維持することができるとされています。また、認知行動療法は副作用が少ないため、安全に継続して受けることができます。
【生活習慣の改善】
生活習慣の改善は、睡眠障害の改善に大きな影響を与えることが知られています。
規則正しい生活リズムの確立や適切な運動、バランスの取れた食事などが重要です。
ストレス管理も睡眠障害改善のポイントです。ストレスが溜まると自律神経のバランスが崩れ、睡眠に影響を及ぼすことがあります。リラックスする時間を作ったり、ストレス解消法を取り入れることで、睡眠の質が向上する可能性があります。
健康的な生活習慣を身につけることで、睡眠障害の改善や予防につながることが期待されます。
睡眠外来を選ぶ時のポイントは?

睡眠外来を選ぶ際には、以下のポイントに注意すると良いでしょう。
睡眠専門医がいるか
睡眠外来では、睡眠に関する専門知識を持つ医師が診療を行います。
日本睡眠学会が認定した医師や、専門医の資格をもっているかどうか確認することが重要です。また、実務経験や専門知識、最新の治療法に精通しているかどうかもチェックポイントとなります。患者さまとのコミュニケーションが円滑に行えるかどうかも重要な要素です。
適切な診断や治療を受けるために、専門性の高い医師が在籍しているクリニックを選びましょう。
通いやすい場所にあるか
睡眠外来は、通院が必要となることが多いため、通いやすさも重要なポイントとなります。
睡眠障害は関連する疾患の他にも、生活習慣やストレスなどさまざまな要因によって引き起こされるため、一度の治療で改善するというわけではありません。
つまり、定期的に通院が必要になります。そのため、自宅や職場近く、通勤途中にあるなど、ご自身のライフスタイルに合わせたクリニックを選択した方が治療を継続しやすくなるでしょう。
まとめ
睡眠障害は生活習慣やストレスなどさまざまな要因によって引き起こされることがあります。
ここでは、睡眠障害から脱却するために睡眠外来を紹介しました。
睡眠外来を受診する際は、専門性も重要ですが、ご自身の症状や悩みをしっかりと伝えることで、より適切な治療を受けることができます。医師やスタッフとのコミュニケーションを大切にし、睡眠障害に向き合いましょう。




