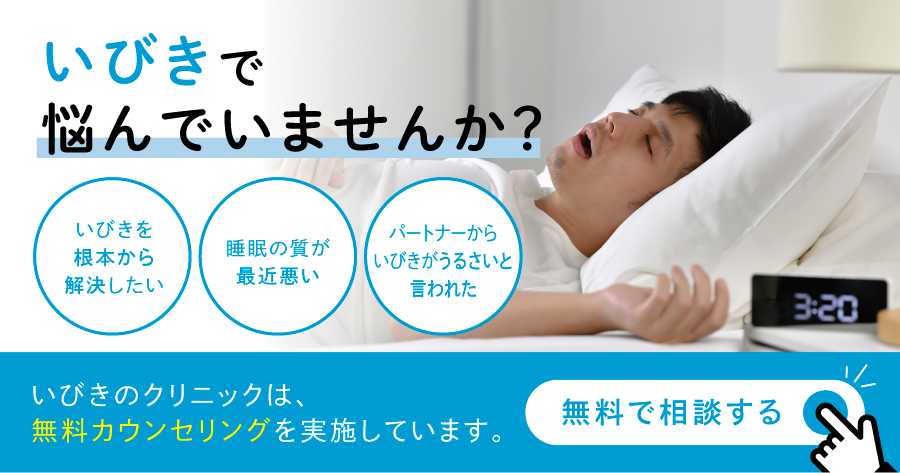[経歴]
2012年3月 兵庫医科大学医学部 卒業
2012年4月 高知医療センター勤務
その後、大手美容外科にて院長を歴任
2024年2月 いびきのクリニック入職
2024年11月 いびきのクリニック梅田院院長となる
- いびきのクリニックTOP
- いびきのコラム
- いびきを治す方法10選!いびきの原因や即効性のある対策も紹介!
いびきを治す方法10選!
いびきの原因や即効性のある対策も紹介!

いびきの原因やメカニズムを理解することで、適切な対策や治療法を見つける手助けになります。
口呼吸や睡眠時の姿勢、体重管理など、生活習慣の見直しやいびき対策グッズの活用などが、いびき改善に役立つことがあります。
睡眠時の呼吸の問題は軽視せず、健康な睡眠を取るためにも適切な対策を行いましょう。
監修医師情報

いびきはなぜ起きる?

いびきのメカニズムは、睡眠時に気道が狭くなることで、通常よりも空気の流れが制限されることによって生じます。この狭窄が起こる原因には、睡眠中の筋肉の緩み、口呼吸、アレルギー反応、肥満などが挙げられます。
いびきをかく原因は?

いびきの主な原因は、口呼吸や睡眠姿勢などさまざまな要因が関与しています。ここでは、いびきの主な原因について詳しく見ていきましょう。
飲酒
飲酒はのどの筋肉を弛緩させ、気道を狭めることがあります。これにより、睡眠中にのどの組織が振動しやすくなり、いびきが発生しやすくなるのです。
また、アルコールが睡眠の質を低下させ、深い眠りに入ることを妨げるため、いびきが一層ひどくなることがあります。特に眠る前に寝酒として飲酒する習慣がある人は要注意です。寝酒をするといびきを引き起こしやすくなります。
喫煙
喫煙はのどの粘膜を刺激し、炎症を引き起こすことがあります。この炎症によってのどの通り道が狭くなり、いびきの原因となることがあります。
さらに、喫煙によって気道の筋肉が弛緩しやすくなるため、いびきが発生しやすくなることもあります。
疲労
長時間の労働などで疲労が蓄積すると、体全体の筋肉が緊張しやすくなります。特に、喉の筋肉が緩むことで気道が狭くなり、いびきを引き起こします。疲労が原因でいびきをかく場合、十分な休息と睡眠が必要です
病気
いびきが続くことで、睡眠時無呼吸症候群(SAS)という症状を引き起こす可能性があります。睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に一時的に呼吸が止まる状態であり、これが長期間続くと高血圧や心臓病、脳卒中などの病気のリスクを増加させる可能性があります。
枕の位置
枕の高さもいびきに影響を与えます。高すぎる枕は首を圧迫し、気道を狭くする原因となります。一方、低すぎる枕も頭が後ろに倒れやすくなり、気道が狭くなります。
手を挙げて寝る
両腕を上げてバンザイの格好で寝るバンザイ寝も、気道が狭くなるのでいびきをかきやすくなります。
口呼吸
口呼吸は、鼻呼吸に比べてのどや口の粘膜が乾燥しやすくなるため、いびきの原因となります。
口呼吸を習慣化すると、のどの筋肉が緩んで口が開きやすくなり、気道が狭くなっていびきが発生しやすくなります。口呼吸を改善することで、いびきを軽減することが期待できます。
風邪
風邪をひくと鼻づまりが起こりやすく、口呼吸になるため、いびきを引き起こします。また、のどの炎症が起こり、いびきが増えることがあります。
鼻づまり
鼻づまりが原因で口呼吸になることも多く、アレルギーや風邪、鼻中隔の偏りなどが鼻づまりを引き起こします。鼻づまりが続くと口呼吸になってしまうため、慢性的ないびきの原因となります。
女性ホルモンの減少
女性ホルモンと睡眠の関係性には興味深い研究結果があります。
女性ホルモンのプロゲステロンは、気道を広げる作用がありますが、更年期などでプロゲステロンが減少すると気道が狭くなりいびきの発生につながることが分かっています。
体重の増加
太ると首周りや舌、喉の脂肪が増え、気道が圧迫されます。すると空気が通るときに音が生じ、いびきとなってしまうのです。特に仰向けで寝ると重力によって舌がのどに落ち込みやすくなり、気道が狭くなるため、いびきを引き起こしやすくなります。
いびき対策10選!

いびきを自覚しているのなら、適切な対策を講じることで、快適な睡眠を取り戻しましょう。
ここではいびき対策を10個紹介します。
【今すぐできるいびき対策】
いびきは自分だけでなく周りにもストレスをかけてしまいます。
すぐに対策できるものから試してみてください。
1.横向きで寝てみる
横向きで寝ることは、いびきを防ぐ最も効果的な方法の一つです。横向きになることで、舌や軟口蓋が喉の奥に落ち込むのを防ぎ、気道が確保されやすくなります。
仰向けで寝ると、舌や喉の筋肉が重力で後方に落ち込み、気道を狭くすることがあります。
抱き枕を使うことで、体が安定し、横向きの姿勢を維持しやすくなります。また、無意識に仰向けになるのを防ぐことができます。
寝る姿勢を工夫することも対策の一つです。
2.寝具を変えてみる
寝具の選び方も、いびき対策に大きな影響を与えます。高さが適切な枕を選び、寝る姿勢を工夫することで、気道を確保しやすくなります。
寝具は通気性の良いものを選び、寝室の温度や湿度を適切に保つことが重要です。
自分に合った枕や寝具を選ぶことで、快適な睡眠環境を整え、いびきの発生を抑えることができます。
3.寝室の環境を変える
寝室の環境も睡眠には重要です。
寝室の室温は18〜22度が理想的とされています。また、湿度は40〜60%を保つことが重要です。乾燥した空気は鼻や喉の粘膜を刺激し、いびきを引き起こしやすくなります。加湿器を使用することで、適切な湿度を保つことができます。
4.寝酒をしない
いびき対策の一つとして「寝酒をしない」ことが挙げられます。
寝る前の数時間はアルコールを摂取しないように心がけましょう。特に、寝る直前の飲酒は避けるべきです。
5.生活習慣を変える
規則正しい生活習慣を維持することで、自然な眠りを促進することができます。
毎日同じ時間に寝起きすることや、バランスの取れた食事を心がけることが重要です。
生活習慣改善の一環として、飲酒や喫煙を控えることもいびき改善につながります。
6.肥満を解消する
肥満によっていびきは悪化します。そのため、肥満体型の方にはダイエットをおすすめします。
肥満は睡眠時無呼吸症候群のリスクも高まるため、体重管理がとても重要です。
栄養バランスの取れた食事を心がけ、過剰なカロリー摂取を避けてください。野菜や果物、タンパク質をバランスよく摂取するようにしましょう。また、夕食は寝る3時間前までに済ませることが望ましいです。
定期的な運動は、体重管理に効果的です。ウォーキングやジョギング、筋力トレーニングなどを取り入れましょう。
7.口の周りや舌の筋肉をトレーニング
口の周りや舌の筋肉を鍛えることで、いびきを軽減することができます。簡単なトレーニング方法としては、舌を上あごに押し付けたり、口を大きく開けて閉じる運動があります。これらのトレーニングを日常的に行うことで、筋肉が強化され、いびきの改善が期待できます。
8.いびき対策グッズを使う
市販されているいびき対策グッズを利用するのも一つの方法です。例えば、いびき防止枕やマウスピース、鼻孔拡張テープ、いびき防止マスクなどがあります。
これらのグッズを試してみることで、自分に合った対策を見つけることができるでしょう。
【病院で行うことができるいびき治療】

病院でできるいびきの治療は、
- CPAP療法(Continuous Positive Airway Pressure)
- 手術
- 歯科矯正
などがあります。
重度のいびきや睡眠時無呼吸症候群の場合には、CPAP療法が選択されることがあります。
一部の患者には手術が適している場合もあります。また、歯科矯正によって、下顎を前方に移動させることで気道を広げることもがあります。
このような病院でしかできない治療も一つの選択肢として念頭に置いておくのも良いでしょう。
9.外科手術を受ける
いびきの基本的な対策は保存的対応になりますが、それでも改善されない場合は、手術を選択することがあります。その場合、終夜睡眠ポリソムノグラフィ検査(PSG)で問題点を確認したうえで、手術の適応の判断をします。
主に行われる手術は、咽頭口蓋形成術、口蓋垂咽頭口蓋形成術(UPPP)、扁桃腺摘出手術、アデノイド切除術などです。特に子供では扁桃肥大が原因のいびきが多く見られるため、扁桃腺摘出手術がよく行われます。
手術はリスクが伴うため、慎重な検討が必要です。
10.ナステント
ナステント治療は、鼻腔内に装着される装置を用いて睡眠時の呼吸を改善する治療法です。
この装置は、気道を開いて通気を良くすることで、睡眠時の無呼吸症候群や低酸素症を改善します。
ナステント治療は、CPAP治療に比べて装着感が軽減されるという利点があります。
まとめ
いびきの原因やメカニズムを理解することで、適切な対策や治療法を見つける手助けになります。
口呼吸や睡眠時の姿勢、体重管理など、生活習慣の見直しやいびき対策グッズの活用などが、いびき改善に役立つことがあります。
睡眠時の呼吸の問題は軽視せず、健康な睡眠を取るためにも適切な対策を行いましょう。
いびきが続く場合はまずは医療機関に相談してみましょう。